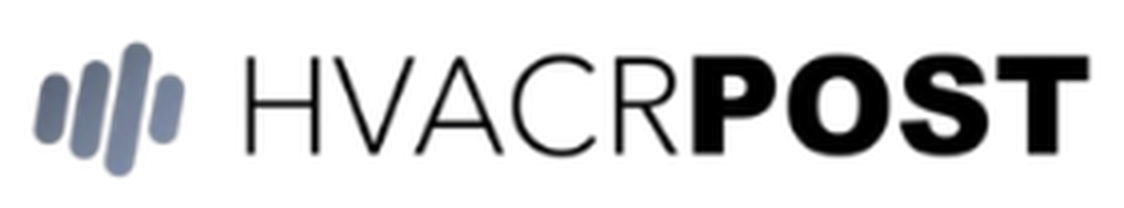- 冷媒は性能や環境負荷によりHFC、HFO、自然冷媒、混合冷媒に分類される。
- 欧州の規制により、低GWP冷媒への移行が進み、Daikinはその先頭に立つ。
- R-1234zeやR-32を用いた新型ヒートポンプが持つ性能と可能性を紹介。
脱炭素社会に向けた冷媒技術の進化とDaikinの取り組み
冷媒は、ヒートポンプやエアコンなどの空調機器において、熱を移動させるための重要な要素です。これまで主流だったHFC(R-134aやR-410A)は、性能は高いものの、温室効果ガスとしての影響が大きく、GWP(地球温暖化係数)の高さが環境面で課題とされてきました。
こうした背景を受けて登場したのが、HFO(例:R-1234yf、R-1234ze)や自然冷媒(R-744=CO₂、R-290=プロパン、R-717=アンモニア)といった、GWPが極めて低い、あるいはゼロに近い冷媒です。これらはオゾン層破壊係数(ODP)がゼロであることも特長で、脱炭素社会の実現に向けた有力な選択肢とされています。
さらに、安全性や冷媒効率、環境性能のバランスを取った混合冷媒(例:R-454C、R-513A)も登場し、用途に応じた最適な選択が進んでいます。
欧州の規制強化と冷媒の転換加速
欧州ではFガス規制の強化が進み、2027年にはR-134aやR-410Aといった高GWP冷媒の使用が原則禁止される見通しです。こうした規制により、より環境負荷の少ない冷媒への切り替えが急速に進んでいます。
このような動きを受け、R-32やR-1234zeといった次世代冷媒の採用が加速しています。R-32は比較的扱いやすく、エネルギー効率も高いため、特に住宅用エアコンなどで急速に広まっています。
ダイキンの先進的な取り組み
こうした流れの中で、空調業界のリーダー企業であるダイキンは、冷媒の低GWP化を積極的に推進しています。同社は以下のような先進製品を展開し、脱炭素と高効率の両立を実現しています:
- EWYE-CZ(空気熱源ヒートポンプ)
使用冷媒:R-454C
特長:最大70℃の高温給湯に対応し、–25℃の極寒環境でも稼働可能。住宅や商業施設向けに設計。 - EWWH-VZ(水熱源ヒートポンプ)
使用冷媒:R-1234ze
特長:最大90℃の高温給湯を実現し、食品加工や医療などの産業用途にも対応。
これらの製品は、単なる機器性能だけでなく、省エネ性・持続可能性・柔軟な運用性といった観点でも高い評価を受けています。
今後の展望と社会的インパクト
冷媒技術の進化は、今後の脱炭素社会に不可欠な要素の一つです。特に、自然冷媒や超低GWP冷媒を活用したソリューションは、住宅用途だけでなく、産業分野や地域の冷暖房(地域熱供給)においても活躍の場が広がっていくと考えられます。
ダイキンのように、環境対応技術の開発と普及を牽引する企業が市場をリードすることで、空調業界全体の低炭素化が一層加速し、よりクリーンで持続可能な社会の実現が期待されます。Daikinのような先進企業がこの流れを牽引することで、よりクリーンで持続可能な社会の実現が期待されます。
重要キーワード3つの解説
- GWP(Global Warming Potential):地球温暖化への影響度を示す指標。数値が小さいほど環境への負荷が低い。
- HFO(ハイドロフルオロオレフィン):新世代冷媒で、HFCよりも大幅に低いGWPを持ち、規制対応にも適している。
- 自然冷媒:アンモニア、二酸化炭素、プロパンなどの天然由来冷媒。高性能だが、取り扱いに安全対策が必要。
その他の記事
-
Daikin、ロンドンで最新データセンター冷却技術を発表 ― AI時代の省エネと持続可能性を両立
-
ダイキンアプライド、データセンター向け冷却技術を強化 ― DDCソリューションズを買収
-
冷媒漏れ検知、これ一台で冷暖房システムの漏れを発見!Fieldpieceの新型ガスリークディテクター「DRX3」登場
-
エアコン冷媒が血液に? 拡散するTFAの驚くべき実態 (HFO-1234yf)
-
中国のHCFC全廃計画とHFC削減戦略—グリーンクーリング行動計画の全貌
-
冷媒漏えいの影響を数字で見る—直接排出と間接排出の関係
-
冷媒規制の最前線—モントリオール議定書とEUの独自規制が描く未来
-
冷媒の選択肢と課題—低GWP化と可燃性リスクのバランス
-
EUが進める冷媒機器の販売・サービス禁止強化—輸出規制からヒートポンプ市場まで
-
米ロードアイランド州の水道水の3分の2からTFAを検出:新たなPFAS汚染の実態