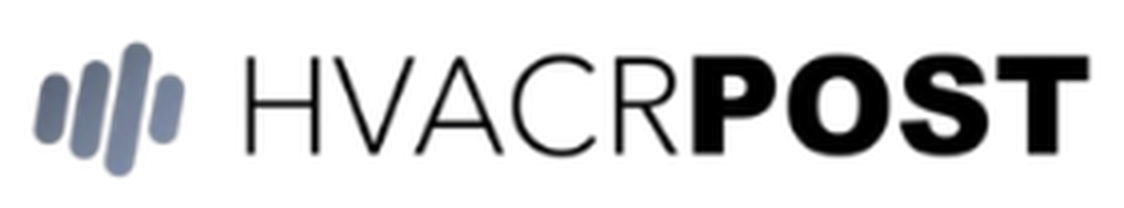- 自然冷媒システムの導入には専門的な技術者教育が不可欠
- 欧州ではFガス規制により認証制度の導入が義務化
- GIZやUNDPなど国際機関が新興国で積極的に研修を実施
- 米国でもメーカーとNPOが連携し無償の研修サミットを開催
- 冷媒技術者の育成は脱Fガスの鍵としてますます重要に
脱フロン時代に対応した冷媒技術者の育成が、世界各地で本格化
自然冷媒(アンモニア、CO₂、プロパンなど)の導入を加速させる上で、技術者の専門教育は不可欠とされています。CO₂は高圧対応の難しさ、プロパンは可燃性のリスクがあり、適切な知識と技能が求められます。
2024年3月に改正されたEUのFガス規制では、自然冷媒を扱う技術者に対する認証制度が義務付けられました。これにより、各国での制度整備が進められています。
ヨーロッパ以外でも、ドイツの国際協力機構GIZはベトナムやホンジュラスでプロパン冷凍システムのワークショップを開催。ブラジルの技術者をドイツへ招き、CO₂の最新技術に関する研修も行いました。
また、国連開発計画(UNDP)の「Cool Up」プログラムでは、エジプトやトルコ、ヨルダンで自然冷媒に関する技術研修が実施されました。アメリカでは、NASRC(北米持続可能冷媒協議会)とメーカーが協力し、CO₂やプロパンをテーマにした無料研修サミットが全米で開催されました。
このような多国間の取り組みにより、今後さらに多くの冷媒技術者が育成され、脱Fガス社会への移行が加速すると見られています。
キーワード
- 自然冷媒:地球温暖化係数が極めて低く、環境負荷が少ない冷媒。代表的なものにアンモニア、二酸化炭素(CO₂)、プロパンがある。
- Fガス規制:フルオロカーボン類(HFCなど)の排出抑制を目的としたEUの法規制で、自然冷媒の導入促進もその一環。
- GIZ(ドイツ国際協力機構):開発途上国における持続可能な技術普及を支援するドイツ政府の国際協力機関。自然冷媒分野でも積極的に研修を展開中。
その他の記事
-
冷媒漏れ検知、これ一台で冷暖房システムの漏れを発見!Fieldpieceの新型ガスリークディテクター「DRX3」登場
-
エアコン冷媒が血液に? 拡散するTFAの驚くべき実態 (HFO-1234yf)
-
中国のHCFC全廃計画とHFC削減戦略—グリーンクーリング行動計画の全貌
-
冷媒漏えいの影響を数字で見る—直接排出と間接排出の関係
-
冷媒規制の最前線—モントリオール議定書とEUの独自規制が描く未来
-
冷媒の選択肢と課題—低GWP化と可燃性リスクのバランス
-
EUが進める冷媒機器の販売・サービス禁止強化—輸出規制からヒートポンプ市場まで
-
米ロードアイランド州の水道水の3分の2からTFAを検出:新たなPFAS汚染の実態
-
低GWP冷媒の未来予測—環境・安全・コストを満たす多様な選択肢へ
-
世界で進む冷媒の安全規格強化—可燃性冷媒の受け入れ拡大へ