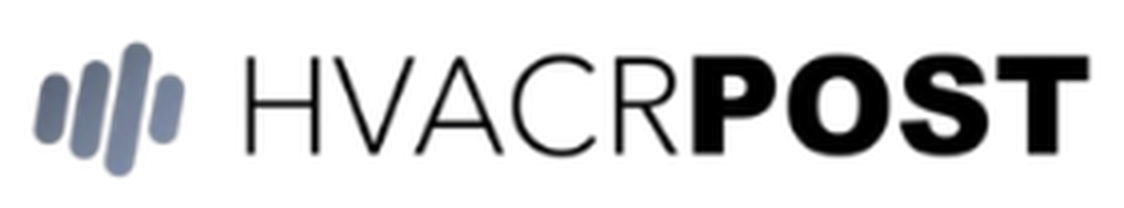温暖化対策の“次世代冷媒”が、実は環境中に新たなリスクをもたらしている
2012年、ヨーロッパでは自動車のエアコン用にHFO-1234yf(2,3,3,3-テトラフルオロプロペン)という冷媒が導入されました。それまで広く使われていたHFC-134aに代わる存在として期待され、さらにR513AやR449Aといった混合冷媒にも取り入れられました。この十数年間で、HFO-1234yfは世界最大級のTFA発生源となっています。
その背景には温室効果ガス削減の流れがあります。HFO-1234yfは地球温暖化係数(GWP)が非常に低く、100年基準で1.81、20年基準ではわずか0.501とされています(IPCC第6次評価報告)。一見すると環境に優しい冷媒のように見えますが、問題は大気中に放出された後にあります。HFO-1234yfは100%が光酸化反応によって、わずか10〜14日でTFAに変化してしまうのです。
同じHFOでもHFO-1234zeは20日程度でTFAを生成しますが、その量は1割以下と比較的少なめです。それでもTFAへの変化は避けられません。
大気中での光酸化の影響は、2024年に発表された研究で明確に示されました。研究チームは北極圏スピッツベルゲン島の雪を2019年1月から8月にかけて採取し、24時間真っ暗な時期と24時間明るい時期を比較しました。その結果、太陽光のある時期のTFA濃度は暗い時期の最大71倍にも達していたのです。つまり、光がある環境では冷媒ガスが急速にTFAへと姿を変え、地球規模で拡散していることが裏付けられました。
さらにHFOや冷媒以外にもTFAを生み出す経路は存在します。たとえば一部の農薬や医薬品の分解、下水処理や工場排出など、複数の人間活動がTFAの汚染を加速させています。こうして環境中に広がったTFAは、雨水や川を通じて最終的に私たちの飲料水や食べ物にまで届くのです。
重要キーワード3つの解説
- HFO-1234yf
2012年に導入された次世代冷媒。温暖化係数が極めて低いが、大気中でほぼ全量がTFAに変わるため新たな環境リスクを生む。 - 光酸化反応
大気中で太陽光エネルギーを受け、冷媒や他の化学物質が分解される現象。HFO-1234yfがTFAになる主要なプロセス。 - TFA(トリフルオロ酢酸)
強い持続性を持つ化学物質で、分解されず環境中に蓄積する。水や食物連鎖を通じて人間や生態系に広がる。
今後の展開とインパクト
HFO-1234yfは「温暖化対策の救世主」として導入されたものの、環境中に必ずTFAを生むという“見えない副作用”を抱えています。特に自動車の普及とともにその使用量は急増しており、今後もTFAの蓄積が加速する恐れがあります。EUでは規制に向けた議論が本格化していますが、世界全体での合意には時間がかかるかもしれません。もし放置すれば、将来的に飲み水や食の安全に長期的な影響を与え、人間の健康や生態系の持続可能性を根本から揺るがす可能性があるのです。