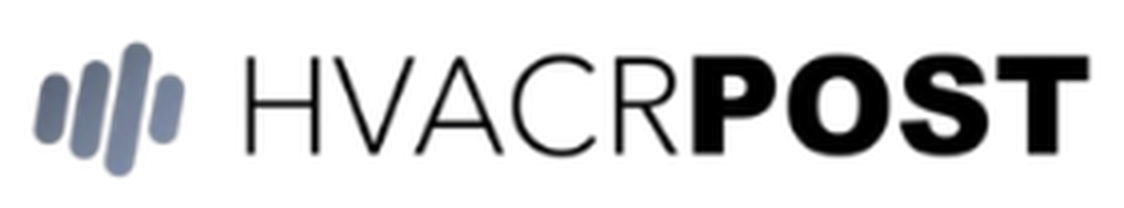HFC代替をめぐる新冷媒の開発は加速中。A2LやHFO、天然冷媒の採用が広がる一方、安全管理の重要性も増す。
高GWP(地球温暖化係数)の冷媒を廃止する流れが強まる中、業界はさまざまな代替冷媒を導入しています。しかし、多くの場合、GWPの低下と可燃性の上昇がトレードオフの関係にあります。従来の非可燃性冷媒には単純な低GWPの代替品がなく、低GWPで高冷却能力の冷媒ほど可燃性が高まります。
HFCのGWPを下げる主な方法は、化学的に不飽和構造(ダブルボンド)にすることで、大気中に放出されても速やかに分解されるようにすることです。この不飽和型FガスはHFO(ハイドロフルオロオレフィン)と呼ばれ、代表的なものにR1234yf、R1234ze(E)、R1233zdがあります。これらはGWPが極めて低く、非可燃または軽度可燃(A2L)に分類されます。一方で、純粋な高密度HFO(例:R1132(E))は安定性が低く、単独では使用できません。そのため、HFOとHFCを混合(ブレンド)して性能と安全性のバランスを取ります。
ASHRAE 34規格では冷媒を毒性(A/B)と可燃性(1/2L/2/3)で分類します。例えば、
- A1:非可燃・低毒性(従来の代表的HFCが該当)
- A2L:低可燃・低毒性(炎の伝播速度 < 10cm/s)
- A3:高可燃・低毒性(炭化水素系冷媒など)
- B2L/B2:低燃性または燃性・高毒性(アンモニアなど)
炭化水素は低毒性ですが高可燃性で、特別な安全措置が必要です。アンモニアは可燃性は低いものの高毒性で、主に産業用冷凍で高効率性から使用されています。
A2L冷媒は、既に高GWP HFC代替として広く使われ、主要な機器部品も対応製品が揃っています。特にR1234ze(E)は30℃以上でのみ可燃性を持つ特殊なA2L冷媒で、EN 378規格上はEU PED指令のPED Group 2流体として扱われ、配管や部品の材料追跡義務(トレーサビリティ)が32mm径まで不要になります(他の可燃性冷媒は25mmから義務化)。
可燃性冷媒を扱うシステムでは、安全規格に基づいた設計が不可欠です。万が一漏えいし、可燃性雰囲気が発生する恐れがある場合は、着火源を除去または非可燃区域へ移す必要があります。そのため、防爆認証(EX)取得部品の使用が有効です。EU向けにはASERCOMが主要メーカーの知見を集めたガイドラインを提供しており、設計やメンテナンス時の参考になります。なお、サービス作業時は全ての着火源を切ることが必須です。
今後の展開とインパクト
- A2L・HFO冷媒は高効率かつ低GWPで普及が加速するが、可燃性対策が不可欠。
- 特殊性のあるR1234zeなどは、法規上の取り扱い優遇により採用が進む可能性。
- 防爆部品の標準化や施工ガイドラインの普及が、可燃性冷媒の安全利用を後押し。
- 市場や地域の条件に応じたデュアル戦略(複数冷媒の併用)が現実的な選択肢となる。
重要キーワード3つの解説
- HFO(ハイドロフルオロオレフィン)
不飽和結合を持つ新型Fガス。GWPが非常に低く、分解が早い。例:R1234yf、R1234ze(E)。 - A2L冷媒
炎の伝播速度が10cm/s未満の低可燃性冷媒。安全対策次第で幅広く利用可能。 - 防爆認証部品(EX認証)
可燃性ガス雰囲気での着火を防ぐ特別設計部品。可燃性冷媒システムの安全対策に不可欠。
その他の記事
-
冷媒漏れ検知、これ一台で冷暖房システムの漏れを発見!Fieldpieceの新型ガスリークディテクター「DRX3」登場
-
エアコン冷媒が血液に? 拡散するTFAの驚くべき実態 (HFO-1234yf)
-
中国のHCFC全廃計画とHFC削減戦略—グリーンクーリング行動計画の全貌
-
冷媒漏えいの影響を数字で見る—直接排出と間接排出の関係
-
冷媒規制の最前線—モントリオール議定書とEUの独自規制が描く未来
-
冷媒の選択肢と課題—低GWP化と可燃性リスクのバランス
-
EUが進める冷媒機器の販売・サービス禁止強化—輸出規制からヒートポンプ市場まで
-
米ロードアイランド州の水道水の3分の2からTFAを検出:新たなPFAS汚染の実態
-
低GWP冷媒の未来予測—環境・安全・コストを満たす多様な選択肢へ
-
世界で進む冷媒の安全規格強化—可燃性冷媒の受け入れ拡大へ