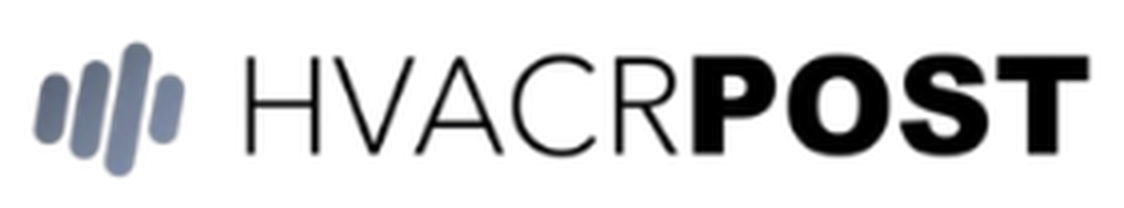炭化水素冷媒にとって「大きな進歩」とされる欧州安全規格改訂、その背景と今後の影響
欧州標準化委員会(CEN)が公開した新しいEN 378の草案版(prEN 378:2025)は、冷凍・空調・ヒートポンプシステムにおける設計や運用の基準を大きく見直す内容となっています。今回の改訂は、従来の2016年版を更新するもので、特に天然冷媒、なかでも炭化水素系冷媒にとって大きな前進と評価されています。
英国のコンサルティング会社Re-phridgeのダニエル・コルボーン氏は、Eurammon主催のウェビナーで「これまでの規格はCO₂(R744)やアンモニア(R717)には対応できていたが、炭化水素にとっては障害となっていた」と指摘しました。その上で、今回の改訂案は炭化水素冷媒の利用拡大につながると強調し、各国の標準化機関に対し承認を後押しするよう働きかける必要性を訴えています。
草案はすでに7月3日に公開され、9月25日までコメントと投票を受け付けており、最終的な採択は2026年に予定されています。内容は「定義・料金制限」「設計・試験」「設備」「冷媒データ」の4部構成で、特にパート1の改訂が注目されています。ここでは冷媒量の計算方法や数量制限、安全限度の考え方などが見直され、柔軟でリスクベースの設計が可能になる見込みです。
欧州の業界団体Eurammonも、この改訂を歓迎しつつ、充填量制限や安全上限に関してさらなる改善を求めています。なぜなら、過度に厳しい制約が依然として天然冷媒の幅広い利用を妨げる恐れがあるからです。
日本の関係者にとっても、この規格改訂は無関係ではありません。国際規格との整合性が強まれば、製品開発や輸出戦略に直接影響する可能性があります。さらに、炭化水素冷媒の適用範囲が広がれば、脱フロン規制やカーボンニュートラル政策に追い風となり、日本企業の技術や市場戦略にも大きなインパクトを与えるでしょう。
重要キーワードの解説
- EN 378:欧州で広く使われる冷凍・空調・ヒートポンプ機器の安全規格。システム設計から運用までをカバーし、国際的な参照基準となっている。
- 天然冷媒:CO₂、アンモニア、炭化水素など自然界に存在する物質を使った冷媒。地球温暖化係数(GWP)が低く、持続可能性の観点から注目されている。
- 炭化水素冷媒:プロパンやイソブタンなどを指し、高い冷却性能を持つ一方で可燃性が課題とされる。今回の規格改訂により、利用拡大が進む可能性がある。