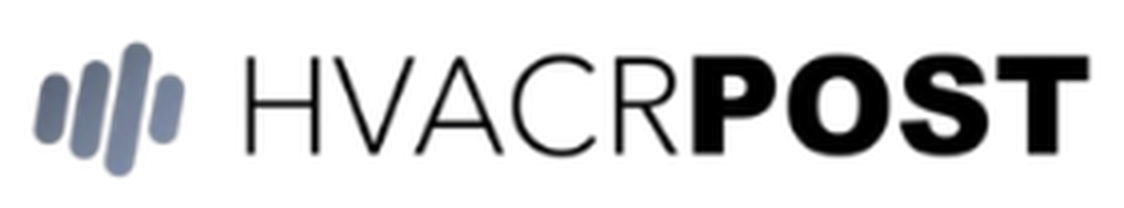ウイルスより「くさい部屋」がイヤ!?空気の見えない不安が消費行動を左右する
アメリカでは今、人々が「におい」や「空気のこもり具合」だけで、お店やジム、学校の信頼度を判断するようになってきています。GPS Airが2025年5月に実施した最新の調査では、41%の人が“変なにおい”を理由に、その場所に二度と行かないと答えました。これは、「その場所でウイルスの感染があった」という情報よりも強く、人の行動を左右しているのです。
一見目に見えないはずの「空気のきれいさ」ですが、人々はもはや「感覚」で判断しています。中でもにおいはとても敏感なサインで、45%の人が“空気がおかしい”と感じるきっかけは、変なにおいだと回答。咳やくしゃみなどよりも、においが信頼を失わせているのです。
そしてこの感覚的な空気判断が、企業や施設にとって新しい課題を生んでいます。56%の人が「自宅の空気の方が信頼できる」と考えており、たった9%しか公共の場所の方が空気管理が優れているとは思っていません。
この「空気への不信感」は、コロナ後の社会では一時的なものではなく、人々の行動やブランドへの信頼、さらには健康意識の根本を大きく変えています。
人々はまた、安心できる証拠を求めています。61%が「空気のモニタリングをしていると知れば安心する」と回答し、65%が「レストランの衛生評価のように空気の質も見える形で表示してほしい」と答えています。学校や空港ではその要望はさらに強く、77%以上が「空気の検査と公開を義務化すべき」だと考えています。
このように、空気の見える化が信頼のカギとなっているのです。
重要キーワード3つの解説
- においによる空気判断
多くの人が空気の状態を「におい」で判断しています。これは科学的なデータよりも直感に頼る傾向が強まっていることを意味しており、変なにおい=危険というイメージが定着し始めています。 - 空気の見える化
人々はもはや「空気はちゃんとしているはず」とは思っていません。数字や表示、モニタリングの証拠を見たいと考えています。これは企業にとっては新たな信頼戦略の一つになり得ます。 - 空気への不信感(エア・ディストラスト)
公共の空間では、空気に対する不安が常に存在しており、「においが気になる」「信用できない」という感覚が行動に直結しています。この不信感は消費者の選択を変え、ブランドの評価にまで影響します。
今後の展開とインパクト
この「空気への感覚的な反応」は、今後さまざまな業界に広がる可能性があります。たとえば、空気のスコアを表示することが当たり前になる時代が来るかもしれません。健康志向のジムやカフェ、子どもを通わせる学校などでは、「空気がきれい」ということが新たな“売り”になります。
さらに企業にとっては、空気管理が信頼やブランドロイヤルティに直結する時代が到来しているとも言えます。におい一つで客が離れ、可視化された空気の質で売上が変わる。そんな時代にどう対応するかが、今後の競争力を左右する重要な要素になるでしょう。