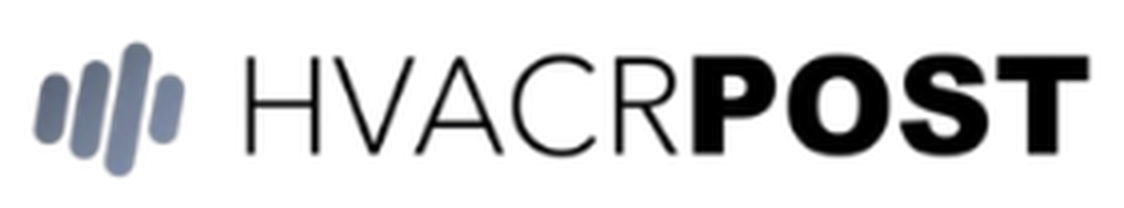フッ素化学の成功から始まった物語は、今や人と環境に迫る大きな課題へと変わった
冷媒ガスとPFAS(有機フッ素化合物)のつながりは、実は発見の初期から存在していました。1930年代、デュポン社が冷媒の実験を行っていた際、偶然にもフライパンの「こびりつかない加工」に使われるPFASを見つけたのです。その後、PFASと冷媒ガスはいずれも“夢の化学物質”として広まり、数十年にわたって産業や暮らしを支えてきました。
しかし1970~80年代に入り、冷媒の一種であるCFCやHCFCがオゾン層を破壊することが明らかになると、1987年のモントリオール議定書で段階的に廃止が決まりました。その代わりに登場したHFCも、今度は強力な温室効果ガスとして問題視され、2016年のキガリ改正で削減が進められることになりました。
一方、2000年代にはPFASの健康被害が次々と指摘されました。その中で、冷媒の一部もPFASに含まれ、さらに分解される過程でTFA(トリフルオロ酢酸)を生み出すことが注目されるようになったのです。
純粋なTFAは工業用の強い酸として利用されますが、吸い込めば有害で、皮膚を焼くほど腐食性があり、水生生物にも長期的な悪影響を与えるとEU規制機関(REACH)により分類されています。構造的には、すでに強い毒性が確認されているPFOAに似ており、TFAも動物実験では低濃度で肝機能障害や酸化ストレスを引き起こすことが確認されています。
実は1993年の時点で、フォード社は冷媒HFC-134aが分解してTFAを生み出す可能性を調べ、「胎児への影響の可能性がある」と報告していました。今年5月にはドイツ政府機関が、TFAは生殖毒性を持ち、非常に持続性が高く、環境中を移動しやすいと正式に評価し、欧州化学品庁に提案しました。その根拠には、母ウサギにTFAを与えた実験で、子ウサギの32%に網膜の異常が見られたという研究結果があります。
さらにラットでは肝機能マーカーの増加や肝臓の肥大が報告され、線虫では酸化ストレスや脂質代謝の乱れが観察されました。加えて、藻類に対しては560ナノグラム/Lという非常に低い濃度でも影響が出ると予測され、農作物の土壌に対しても安全な濃度が定められています。1990年代の研究では、水生生物の体内でTFAがタンパク質に取り込まれてしまうことまで確認されました。
このように、冷媒とPFASの歴史を振り返ると、私たちの暮らしを便利にした技術が、時を経て大きな環境リスクとなって現れていることがわかります。
重要キーワード3つの解説
- PFAS(有機フッ素化合物群)
自然界でほとんど分解されず「永遠の化学物質」と呼ばれる。冷媒の一部もPFASに含まれる。 - TFA(トリフルオロ酢酸)
冷媒が大気中で分解すると生まれる物質。強い腐食性があり、環境中に長く残る。実験では胎児や肝臓への悪影響も報告されている。 - モントリオール議定書とキガリ改正
オゾン層を守るためCFCやHCFCを段階的に廃止し、その後HFCも温暖化対策のため削減を決めた国際的な合意。冷媒規制の歴史的な転換点。
今後の展開とインパクト
今後は欧州を中心にTFAを含むPFASの規制が本格化する見込みです。もし国際的な枠組みが整えば、自動車や冷却産業に大規模な転換が求められるでしょう。一方で、すでに環境中に広がったTFAを取り除くことはほぼ不可能であり、飲み水や食の安全に長期的な影響を及ぼす可能性があります。つまりこれは、化学物質の便利さと引き換えに、人類全体の未来を脅かす問題へと発展しているのです。