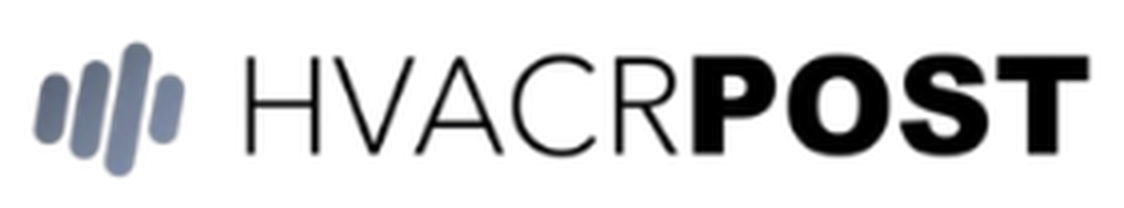「2050年カーボンニュートラル」へ向けた中間ゴール(2040年:少なくとも90%削減)と、建物の電化・低GWP冷媒・最適制御の重要性
まずEuropean Climate Law(欧州気候法)とは、EU全体で2050年までに気候中立(ネットゼロ)を達成するための“土台”となる法律です。目的地(2050年ネットゼロ)だけでなく、そこに迷わず進むための道しるべも用意します。たとえば「2030年の削減目標」や、今回の2040年の削減目標のような中間ゴールを定め、各分野の政策や投資の基準にします。
この流れの中で、欧州委員会は2040年に1990年比で少なくとも90%の排出削減をめざす改正案を出しました。これは法的に拘束力のあるEU共通目標として位置づける案で、合意されれば2030年以降の政策(電力・産業・建物)を一気に“ネットゼロ寄り”に引き上げる効果があります。あわせて、2035年のEU版NDC(パリ協定に基づく目標)もこの2040年目標を踏まえて作られる予定です。
では、HVAC・冷媒の現場に何が起きるのか。まず、建物と産業の電化がこれまで以上に重要になります。電力側の脱炭素が進むほど、ヒートポンプや高効率チラー、熱回収、フリークーリングなど“電気×高効率”の解が主役になります。次に、低GWP冷媒の採用と漏えい低減・回収再生といったライフサイクル管理が、設計・施工・保守の標準要件として定着していきます。さらに、BMS/EMSやAI最適制御で実運用の省エネ(PUEやWUEの改善)を確実に積み上げることが求められます。これらは新築だけでなく、既存建物の改修市場でも強く求められ、モジュール更新や段階的リニューアルへのニーズが高まります。
一方で、議論のポイントもあります。改正案は2040年目標を“域内対策だけ”に限定しないため、国際クレジットの限定的活用(パリ協定Article 6)に道を開く余地があります。ただし、これは競争力や投資配分とのバランスを巡って議論が続いており、最終的な設計は今後の政治プロセスで固まっていきます。いずれにしても、効率化・電化・低GWP・デジタル最適化というHVACの王道はぶれません。むしろ規制対応と市場機会が同時に拡大し、提案仕様の“実装力”が差になります。
日本の関係者にとっては、EU規格・F-Gas動向・省エネ要件への適合を前提に、①低GWP&LCCP最適化設計、②中高温域までカバーする高効率ヒートポンプ/チラー、③AI制御や需要応答・蓄熱を組み込んだ系統連携、④リファービッシュや冷媒回収再生まで含むサービス型ビジネス――この4点を欧州案件の標準装備として揃えることが、営業・設計・保守のすべてで有効です。
重要キーワード3つの解説
European Climate Law(欧州気候法)
EUの2050年ネットゼロを法的に固定し、2030・2040などの中間目標で政策と投資の方向をそろえる“道しるべ”。重要:法的拘束力があり、各分野の規制や支援策の拠り所になる。
2040年「少なくとも90%削減」
1990年比でネット90%以上の削減をEU共通の拘束的目標として設定する改正案。2035年NDCの作成にも直結し、建物・産業の電化と高効率化を後押し。
低GWP冷媒と実運用最適化
F-Gas等の流れと整合し、低GWP化+漏えい抑制+回収再生が必須に。さらにAI制御やBMS連携でPUE/WUEを改善し、実運用での削減を確実にすることが重要。