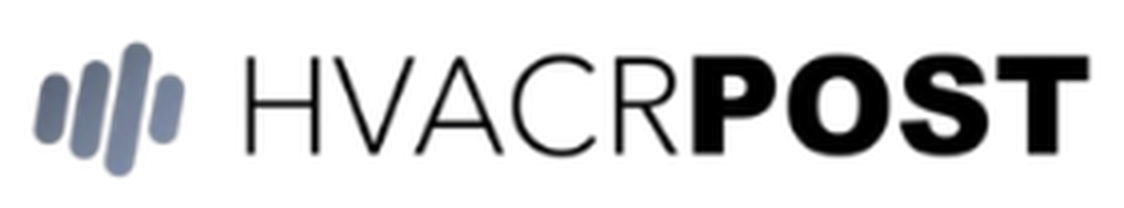欧州需要の高まりに応え、年間70万台規模への生産拡張と自動化を推進
いま欧州では、エネルギー転換と脱炭素の流れを背景にヒートポンプ市場が急成長しています。特にロシアによるウクライナ侵攻以降、化石燃料への依存を減らすことが政治的にも喫緊の課題となり、EU各国は石油やガスに代わる暖房システムへの切り替えを強力に推進しています。その中心にあるのが、空気熱源ヒートポンプ(Air-to-water heat pump)です。大気中の熱を利用してお湯をつくり、暖房や給湯に使う仕組みで、従来の化石燃料暖房と比べてCO₂排出を大幅に抑えられるため、家庭部門の脱炭素化を加速させる切り札とされています。
こうした背景のもと、Panasonicは欧州での需要拡大に対応するため、チェコ・プルゼニの工場に新しい生産棟(約10万㎡規模)を建設し、2025年8月に稼働を開始しました。この工場は1996年にテレビ生産拠点として設立され、2018年からはヒートポンプの室内機を生産、2023年には自然冷媒R290(プロパン)を使った室外機の製造も開始。
新棟の完成により、同工場の生産能力はこれまでの年間15万台から最大70万台規模へと大幅に拡張可能となります。さらに80台のロボット導入による自動化、部品の内製化(熱交換器、銅配管、基板などを工場内で生産し、内製率を約70%に引き上げる計画)によって、コスト競争力と品質管理の両立を目指しています。2028年には部品製造の完全無人化を目標とし、組立工程の自動化率も倍増させる方針です。
環境対応の面でも、同工場は2025年末までにCO₂排出ゼロを達成することを掲げています。その一環として、1MWの太陽光発電設備や自然採光を取り入れる新棟設計を導入しました。Panasonicは2050年のカーボンニュートラル実現を掲げており、この工場は欧州でのヒートポンプ事業拡大だけでなく、持続可能な生産拠点のモデルケースとなります。
欧州では今後、政策的な後押しや補助金制度を背景にヒートポンプの導入がさらに加速する見通しです。Panasonicが現地生産を拡大することは、単なる販売力強化にとどまらず、欧州市場での競争優位性確保、さらには「日本発の技術で欧州の脱炭素を支える」という戦略的意味合いを持っています。
重要キーワード3つの解説
生産自動化・内製化:ロボット活用や主要部品の現地内製によって、コストと品質を安定させる戦略。需給急増に備える上で不可欠。
Air-to-water heat pump(空気熱源ヒートポンプ):外気から熱を取り出し水を加熱、暖房や給湯に利用する省エネ機器。欧州の脱炭素政策で普及が急速に進む。
R290冷媒(プロパン):温室効果係数(GWP)が非常に低い自然冷媒。HFCに代わる環境対応型として欧州規制で導入が拡大中。