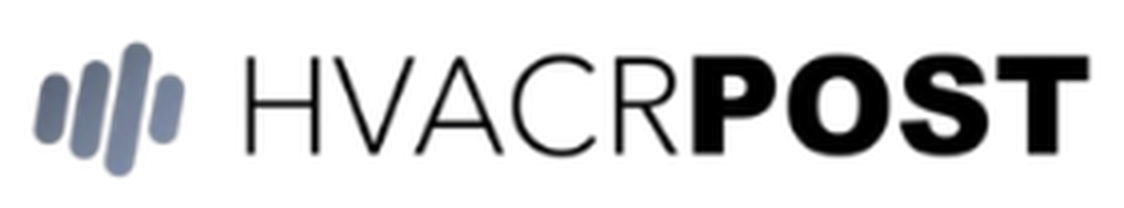地球温暖化対策が急務となる中、冷凍空調の世界でも「自然冷媒」が改めて注目を集めている。フロン規制の強化に伴い、環境負荷の小さい冷媒への転換は産業界にとって避けられない課題だ。
自然冷媒は決して新しい技術ではないが、それぞれに強みとリスクを持ちながら、現代のニーズに応じて再評価されている。アンモニア、二酸化炭素、プロパン──3つの冷媒がどのように使われているのか、その特徴と事例を追ってみたい。
アンモニア(NH₃, R-717)
アンモニアは19世紀から冷媒として使われてきた、いわば「古参」の存在だ。熱効率に優れ、必要量も少なくて済むため、食品工場や大規模冷凍倉庫など、冷凍産業の現場で長く信頼を得てきた。
一方で、その強い刺激臭や毒性は無視できない。漏洩があれば人命に関わるため、厳重な監視システムや安全設計が欠かせない。こうしたリスクを乗り越えてでも選ばれるのは、「大規模で確実に効率を出したい」現場にとって他に代えがたい性能を持つからだ。
米Copeland が乳業工場に導入するという発表があったが、まさにその特長を活かした事例といえる。
二酸化炭素(CO₂, R-744)
CO₂は誰にでもなじみ深い、極めて身近な自然冷媒だ。無毒で燃えないことから安全性が高く、しかも温室効果係数は1。冷媒の中では環境負荷が小さい部類に入る。
ただし、扱いやすさと引き換えに技術的な課題もある。動作圧力は非常に高く、専用の高耐圧機器が必要だ。また、臨界温度が低いため、夏場には効率が落ちやすいという性質も持つ。この高圧特性は、自動車用エアコンなど移動体への応用でも検討が進んでいるが、依然として設計・コスト両面でチャレンジングな課題とされている。
それでも「人が日常的に利用する空間」に向いているのがCO₂の強みだ。スーパーマーケットのショーケースや商業冷蔵、さらにはヒートポンプ給湯器まで、私たちの生活のすぐそばで使われている。
加えて、Hanon Systems が CO₂ 冷媒を用いた電動コンプレッサーの累計生産100万台を突破したことは、EV市場における熱マネジメント需要の広がりを示している。さらに、Hussmann が自然冷媒 CO₂ を用いた冷凍ユニット「Protocol CO2」を発表した例もあり、店舗用途でも導入が加速している。
プロパン(R-290)
プロパンは家庭用ガスとしてもおなじみだが、冷媒としての性能も優秀だ。熱力学特性が良く、環境負荷も非常に小さいため、フロン代替冷媒として注目を集めている。
ただし「高効率の代償」は可燃性だ。火種があれば爆発のリスクがあるため、充填量や設置条件に厳しい制約が設けられている。それでも安全基準を守れば、小型機器で大きな効果を発揮できる。
実際に、IFA 2025 で Midea が家庭用空調に R-290 を採用したモデルを発表するなど、空調機器の分野での展開が始まっている。また、中国の自動車メーカーが EV 向けの二次熱ポンプシステムに R-290 を導入する事例も報告されており、小型かつ効率を求められる分野での普及が進んでいる。